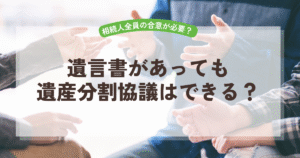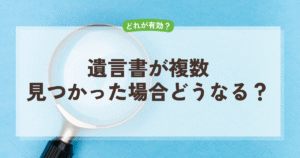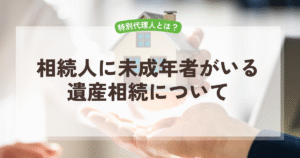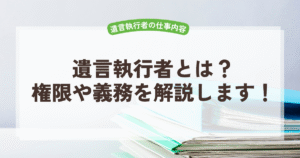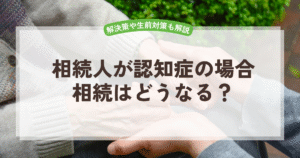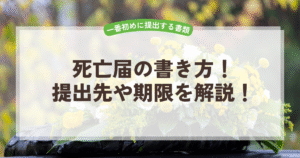相続財産清算人とは?
相続財産清算人とは、相続人の存在が明らかでないとき、相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなったときに、亡くなった方の相続財産を管理する人のことです。
相続財産清算人は、【利害関係人】や【検察官】が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が選任します。
“民法952条(相続財産の清算人の選任)”
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
相続財産清算人の権限・役割
相続財産清算人の権限は、相続財産の保存・管理のみ認められています。
債権者への弁済や財産の処分を行う権限を持ちますが、処分行為には家庭裁判所の許可が必要です。また、特別縁故者への財産分与の手続きを進めることも可能です。最終的に残った財産は国庫に帰属します。
相続財産清算人になる人
相続財産清算人になるために必要な資格はありません。
しかし、被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して、相続財産を清算するのに最も適任と認められる人でなければなりません。また、清算人は多数の法的問題に対応しなければならないため、実際には被相続人が居住していた地域の弁護士や司法書士が選ばれます。
相続財産清算人が必要とされるケース
- 1.相続放棄をしたけど財産管理している場合
-
相続放棄をしたが、財産を現に占有している相続人は、清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければなりません。その保存義務を免れる目的で活用するケースがあります。
- 2.特別縁故者として財産分与を受けたい場合
-
特別縁故者とは、法定相続人ではなく亡くなった方と特別な関係にあった人のことです。具体的には、内縁の妻や事実上の養子、亡くなった方の療養介護をしていた人です。特別縁故者として相続財産を取得するためには、清算人の申立てを行う必要があります。
- 3.債権者として債権の回収をしたい場合
-
通常の場合、債権者が債権の回収をしたいときには、相続人がいれば相続人から回収します。しかし、相続人がいない場合は、回収に困ります。勝手に遺産の中から回収することもできませんし、裁判を起こすにも相手がいないので手続きもできません。そのため、亡くなった人に対して貸金などの債権を持つ債権者が、相続財産から回収するために清算人を選任するケースがあります。
相続財産清算人選任後の流れ
官報で公告し、債権者や受遺者に対して2ヵ月間の公告を行います。債権者・受遺者は、この期間内に申し出をしなければ相続財産を受け取る権利を失います。
申出のあった債権者へ財産を分配し、必要に応じて財産の売却を行います。相続財産をすべて使い切って残余財産がなくなった場合、手続は終了します。
相続人がいない場合、特別縁故者が財産分与を申し立てることができます。分配を希望する特別縁故者は、選任・相続人の捜索公告の期間の終了後、3ヵ月以内に裁判所に対して申し立てる必要があります。
最終的に残った財産は国庫に帰属し、清算人が引き渡し手続きを行います。なお、不動産の共有持分などある場合は、国庫ではなく、ほかの共有者に帰属します。
清算人は家庭裁判所に管理終了報告書を提出し、業務を完了します。
まとめ
本記事では、相続財産清算人とはなにかを解説しました。
相続財産清算人とは、相続人がいない場合に家庭裁判所によって選任され、相続財産の管理・清算を行う役割を担う人です。債権者や受遺者などの利害関係人である場合は、速やかに相続財産清算人の選任の申し立てを行いましょう。
お気軽にご相談ください
お電話で相談をご希望の方
【受付時間】9:00~18:00(土日祝除く)
メールで相談をご希望の方
【受付時間】24時間※後日連絡いたします
FAXで相談をご希望の方
【受付時間】24時間※後日連絡いたします

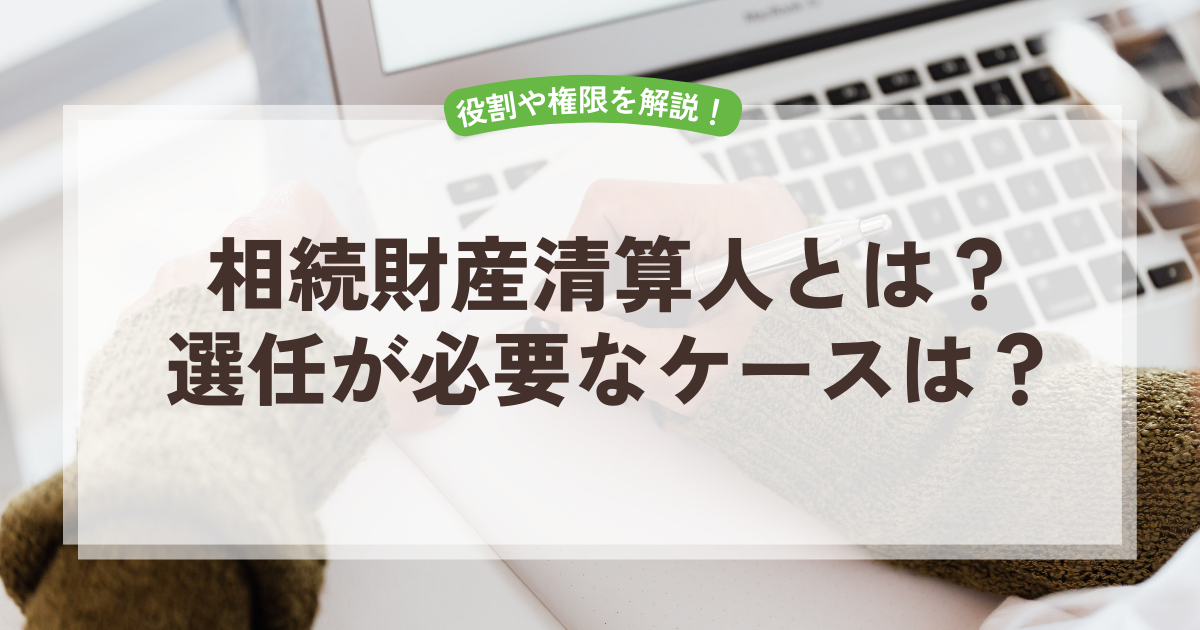
アイキャッチ画像-3-300x158.png)
アイキャッチ画像-300x158.png)