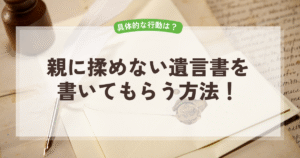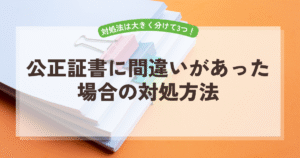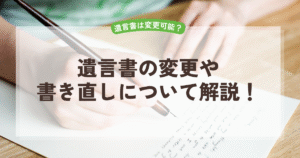亡くなってからは通夜や葬儀の手配、様々な相続手続きが待ったなしで待ちうけており、やらなければならない事が多くあります。大切なご家族が亡くなり精神的な辛さもある中で、相続手続きには期限が決められているものが多く、何から手を付ければいいか分からない…そんな方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続手続きのデジタル遺産にピックアップして詳しく解説します。
- デジタル遺産の内容や具体例
- デジタル遺産の調べ方
- 相続する際の注意点や生前対策の重要性
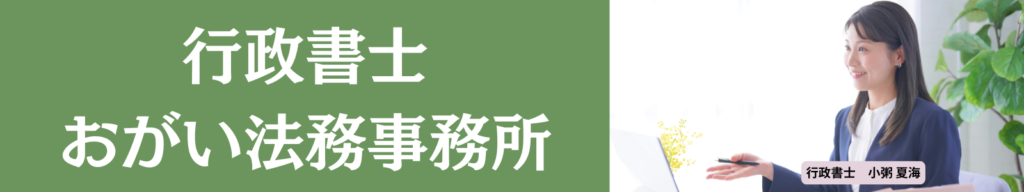
デジタル遺産とは?
デジタル遺産とは、デジタル形式で保管されている遺産です。
データ形式であっても、デジタルで保管された財産も遺産相続の対象となります。
デジタル遺産には財産的価値があるものと、思い出や個人情報としての価値があるものがあります。SNSアカウントや写真データは財産価値は低いですが、暗号資産やネット証券等の残高は大きな財産価値を持ちます。
デジタル遺産の例
デジタル遺産には、さまざまな種類があります。
金融関連のデジタル遺産
- ・ネット銀行やネット証券
-
楽天銀行や楽天証券、住信SBIネット銀行やSBI証券など
- ・仮想通貨(暗号資産)
-
ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)など
- ・電子マネーの残高
-
PayPay、楽天Pay、Suica、LINE Pay、WAON、QUICPayなど
- ・クレジットカードのポイントやマイレージ
-
航空会社のマイル、ショッピングポイントなど
契約・サブスクリプション関連
- ・動画・音楽配信サービス
-
Netflix、Spotify、Amazon Prime Videoなど
- ・クラウドストレージ
-
Google Drive、iCloud、Dropboxなど
- ・オンラインゲームのアカウント
-
Nintendo Switchオンライン、Network、プレイステーションなど
- ・有料会員サービス
-
オンラインサロン、電子書籍の定期購読、デジタルコンテンツなど
知的財産・デジタルコンテンツ関連
- ・NFTアート
- ・ブログやYouTubeの収益アカウント
- ・ドメインやウェブサイトの運営権
- ・電子書籍やデジタル著作物
デジタル遺産を調べる方法
故人のデバイスを確認する
故人が使用していたスマートフォンやパソコンには、デジタル遺産の手がかりが多く含まれています。そのため、アプリやメールの履歴、クラウドストレージの保存データをチェックしましょう。
メールの履歴から、契約中のサービスを特定したり、スマートフォンに金融系アプリがインストールされていないか確認します。また、ブラウザの「閲覧履歴」に、手がかりが含まれている場合もあるのでチェックしましょう。
通帳やクレジットカードの利用明細をチェック
通帳の取引履歴を確認し、ネット銀行や証券口座の入出金履歴を探します。また、クレジットカードの利用明細から、証券会社や仮想通貨取引等の金融サービスの利用履歴をチェックしましょう。
専門家へ依頼する
専門家へ依頼することで、より繊細な調査を行うことが可能です。パスワード解析やデータ復旧は、知識がないと難しい作業となるため、専門家へ相談することも一つの方法です。
デジタル遺産を相続する際の注意点
遺産の存在が気づかれにくい
デジタル遺産は目に見えないため、相続財産として見落とされることがあります。一部の家族だけが情報を知っていた場合、不公平感や疑念から争族に発展することもあります。事前にリスト化しておくことが重要です。
ログインができず相続手続きが進まない
IDやパスワードが不明だと、相続人がアクセスできず、解約や名義変更が難航することがあります。金融機関などは、相続人向けの対応を用意していることもありますが、相続関係を証明する書類等を揃えて提出しなければならない場合がほとんどです。生前にアクセス情報をまとめておくことで、相続人がスムーズに対応できるようになります。
相続手続きに明確な決まりがない場合がある
明確な決まりがあるデジタル遺産
- ネット銀行・ネット証券の口座
- 仮想通貨(暗号資産)
- 電子マネー
以上のようなデジタル遺産は、通常の金融資産と同様扱われ、相続手続きの流れが確立されています。
明確な決まりがないデジタル遺産
- SNSアカウント
- クラウドストレージ
- ブログやYouTubeアカウント
以上のようなデジタル遺産は、各種サービス会社の利用規約によって対応が異なり、サービス会社の規約によっては相続できない場合もあります。事前に契約内容を確認し、必要ならば遺言書や死後事務委任契約書等に明記することで、大切なデジタル遺産を守ることができます。
デジタル遺産の相続対策(生前対策)
遺言書や死後事務委任契約を活用する
前記でも説明した通り、相続のルールが明確でないものもあります。遺言書にデジタル資産の分配方法を明記したり、死後事務委任契約でSNSアカウントやクラウドデータの削除の取決めをしておくことで、自分の希望に沿った相続手続きができます。
デジタル遺産のリスト化しておく
ネット銀行口座、仮想通貨、電子マネー、SNSアカウントなどをリスト化し、ログイン情報(ID・パスワード)を安全な場所に保管しておきましょう。また、リスト化したものは、定期的に更新し、信頼できる家族や専門家に共有することも大切です。
アクセス権の事前設定をしておく
デジタル遺産の内容によって対応は様々ですが、一部のサービスでは「死後のアカウント管理・追悼アカウントの設定」といったような機能があるため、事前に設定しておきましょう。
まとめ
デジタル遺産は現金や不動産といった従来の遺産とは異なり、目に見えにくく、相続手続きが複雑になる場合があるため生前対策が欠かせません。特に仮想通貨や収益アカウントは、アクセスできなければ価値を失う可能性があるので、しっかり準備しておくことが大切です。
デジタル遺産の相続手続きの流れは、一般的な遺産と基本的に同じですが、デジタル遺産の種類や保管サービスの利用規約などに応じて異なる点に注意してください。
お気軽にご相談ください
お電話で相談をご希望の方
【受付時間】9:00~18:00(土日祝除く)
メールで相談をご希望の方
【受付時間】24時間※後日連絡いたします
FAXで相談をご希望の方
【受付時間】24時間※後日連絡いたします


アイキャッチ画像-7-300x158.png)
アイキャッチ画像-6-300x158.png)
アイキャッチ画像-5-300x158.png)
アイキャッチ画像-4-300x158.png)
アイキャッチ画像-2-300x158.png)