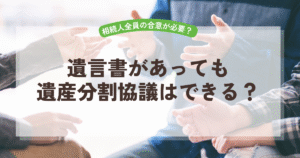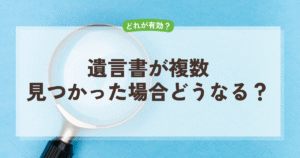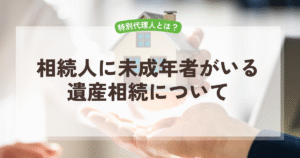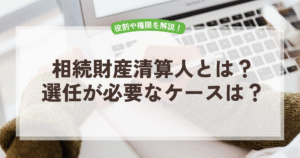相続人に認知症の親がいるけれど、相続手続きはどうやって進めればいいか分からない…。
そうお悩みの方も多いのではないでしょうか?
日本人の平均寿命は右肩上がりで伸びていく中、認知症患者数も年々増加しています。
本記事では、相続人の中に認知症患者がいた場合の相続について分かりやすく解説します。
- 相続人に認知症患者がいる場合の問題点
- 相続手続きを進めるための解決策
- 生前対策の重要性
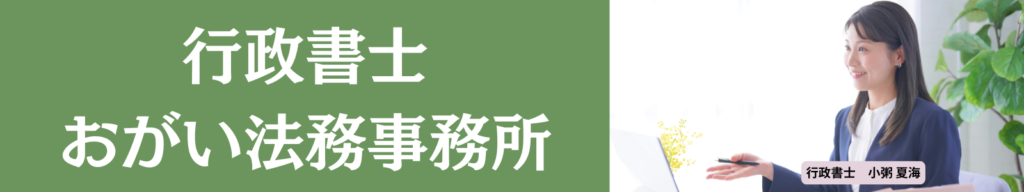
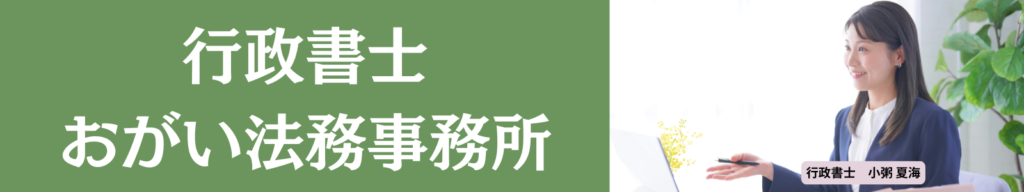
相続の基本
遺産相続とは、「亡くなられた方の財産を引き継ぐこと」です。
遺言書がある場合はその内容が優先されますが、遺言書が無い場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、分け方を決める必要があります。相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。
相続人が認知症の問題点
遺産分割協議ができない
認知症の相続人がした遺産分割協議は無効となる場合があります。
なぜなら、遺産分割協議は法律行為であり、法律行為をするためには意思能力が必要と民法で定められているからです。
認知症といっても、人それぞれ程度があるため、認知症 = 意思能力がない、とは言い切れませんが、法律上では意思能力を有しない者として扱われる場合があることは確かです。意思能力の有無は、個々のケースごとに判断され、具体的な状況や行為の内容によって異なります。
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
この条文を読んでも「認知症の人は法律行為ができない」とは定められていないので、認知症であっても有効な法律行為ができる余地があることが分かります。この場合、意思能力の有無が一番の焦点となり、上記に記載のとおり個々のケースごとに判断となります。認知症患者のご家族が大丈夫だと判断して、遺産分割協議をしても信用が欠けるため、銀行や登記申請での相続手続きが途中でストップしてしまう恐れもあります。必ず医師の診断書をもらって、対応することを考えてください。
遺産分割協議ができないデメリット
不動産が共有名義となる
通常の相続では、相続人の誰かが不動産を単独取得することが一般的です。しかし、遺産分割ができない場合は、不動産を相続する人を決めることができません。そのため、法定相続で登記せざるを得ないことになり、法定相続分の割合で共有状態になってしまいます。
また、相続人の一人が不動産を売却したいと思っても、売却には共有者全員の同意が必要です。共有名義人に認知症の方がいる場合、同意を得られないため、不動産を有効活用することも難しくなってしまいます。
預貯金の解約手続きができない
通常の相続手続きでは、遺産である被相続人名義の預貯金は、解約し、相続人で協議した割合で取得することになります。しかし、意思能力がない認知症の方は自ら銀行の書類に署名することや、委任行為をすることができないので、銀行での預貯金解約時の本人確認の時点で認知症であることを知られることになります。その場合、成年後見人を立てない限り解約ができなくなります。
相続手続きを進める解決策
成年後見制度を利用する
認知症の相続人が含まれる場合の遺産分割協議を行なうには、「成年後見制度」を利用する方法があります。
成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下した方を保護する制度です。
成年後見人という法定代理人(法律の規定によって定められた代理人)を付け、契約や手続きで不利益を被らないよう、本人の代わりに財産管理や契約の代理を行います。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 法定後見制度 | 判断能力がすでに低下している方を対象に、家庭裁判所が成年後見人を選任します。 |
| 任意後見制度 | 将来の判断能力低下に備え、本人が元気なうちに後見人を選び契約を結ぶ制度です。 |
相続発生時に既に相続人が認知症であれば、法定後見制度を利用します。
法定後見制度には、「補助・補佐・後見」の3種類があり、どれに当てはまるかは医師の診断書などを踏まえて家庭裁判所が判断します。
法定後見制度では、家庭裁判所が成年後見人等を選任し、後見内容を決定します。後見開始の審判が下り、所定の手続きを経ると、成年後見人による本人の財産や日常生活の支援・保護が開始され、遺産分割協議も行えるようになります。
成年後見制度のデメリット
成年後見人に対する報酬を一生涯支払う必要がある
法定後見制度を一度活用すると、相続手続きが終了した後も、認知症である本人が亡くなるまでは、法定後見人が財産管理等を継続します。
そのため、成年後見人が専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)の場合、専門家への報酬が発生します。この報酬は本人の財産から支払われ、月額数万円程度になることが一般的です。
後見人は親族以外が選ばれる可能性が高い
成年後見人を選任するのは家庭裁判所です。成年後見制度の申立て時に、家族や親族などを成年後見人候補者として挙げられますが、最終的に成年後見人を選任するのは家庭裁判所です。
仮に、家族や親族が成年後見人に選ばれた場合であっても、利益相反行為になってしまうので注意が必要です。その場合は、監督人が認知症の方の代理をします。また、監督人がいない場合は、再度家庭裁判所にて特別代理人を選任します。
ほかの相続人の意図通りになるとは限らない
成年後見人制度は、本人の財産を守るための制度であることから、成年後見人は法定相続分の割合を重視します。
そのため、節税効果を意識した遺産分割協議等の柔軟な対応が困難となる場合があり、ほかの相続人の意図通りになるとは限りません。
生前対策
有効な遺言書を作成しておく
有効な遺言書があれば、認知症の相続人がいる場合でもスムーズな遺産分割が可能になります。法的効力が強い公正証書遺言を作成しておくことがポイントです。


生前贈与をする
生前贈与を通じて財産を分配することで、相続時の遺産分割協議を避け、家族間の争いを未然に防ぐことができます。贈与者が存命中に意思を伝えることで、家族の納得を得やすくなります。
家族信託を利用する
家族信託とは、財産の管理や運用、処分を信頼できる家族に託す仕組み(契約)のことです。
この制度は、特に認知症などで判断能力が低下した場合でも、財産が凍結されることなく柔軟に活用できるように設計されています。また、家族信託を活用すれば、事前に財産を誰に相続するかを決めておくこともできます。
まとめ
自身の【もしも】の場合に備えて、元気なうちに早めの対策をしておくことが重要です。
「認知症で銀行手続きが止まったらどうしよう…。」「成年後見制度の利用はなるべく避けたい…。」このようなお悩みは一度当事務所へご相談ください。
お気軽にご相談ください
お電話で相談をご希望の方
【受付時間】9:00~18:00(土日祝除く)
メールで相談をご希望の方
【受付時間】24時間※後日連絡いたします
FAXで相談をご希望の方
【受付時間】24時間※後日連絡いたします

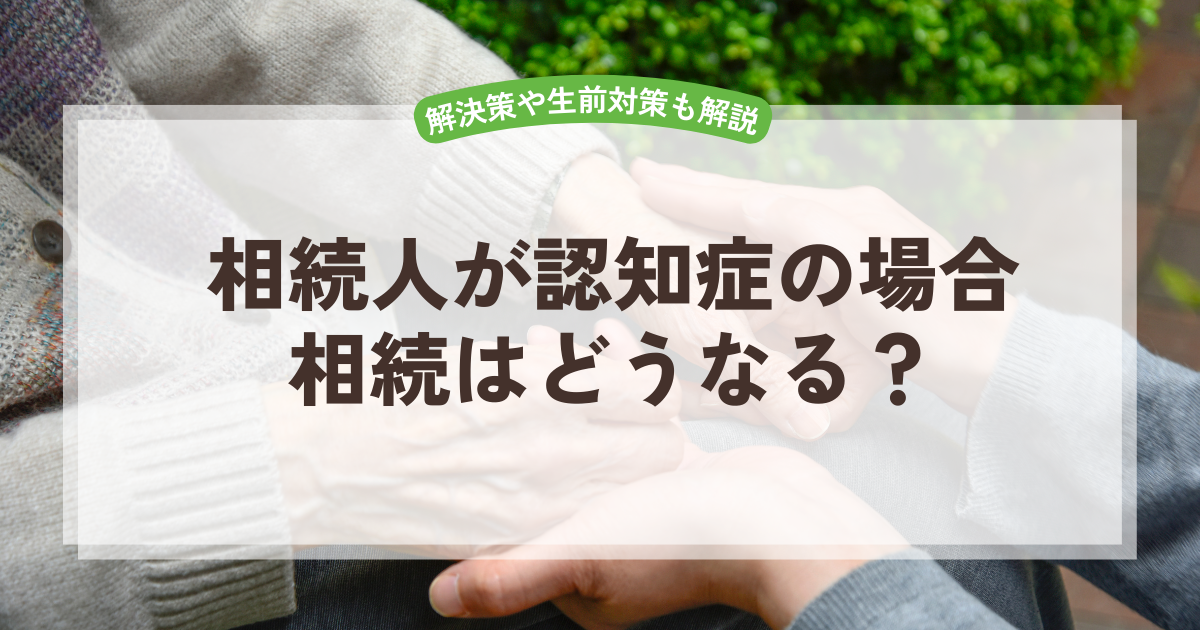
アイキャッチ画像-10-300x158.png)
アイキャッチ画像-9-300x158.png)
アイキャッチ画像-3-300x158.png)
アイキャッチ画像-300x158.png)