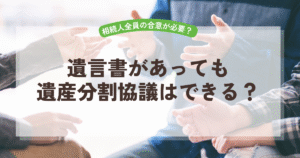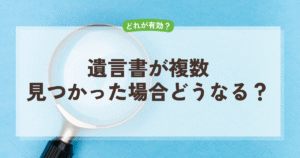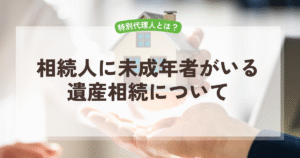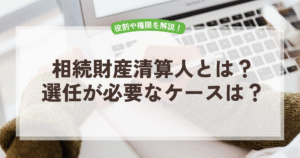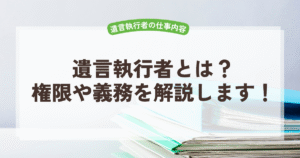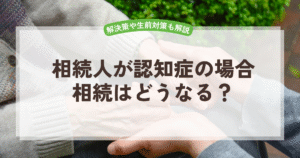遺留分って聞いたことはあるけど、どんなものかよくわからない…。
相続なんて自分にとってはまだ先のことだから、身近に感じない…。
本記事では、遺留分の基礎知識を分かりやすく解説します。
- 遺留分の基本知識
- 遺留分を請求できる相続人の範囲
- 最低限もらえる遺産の割合
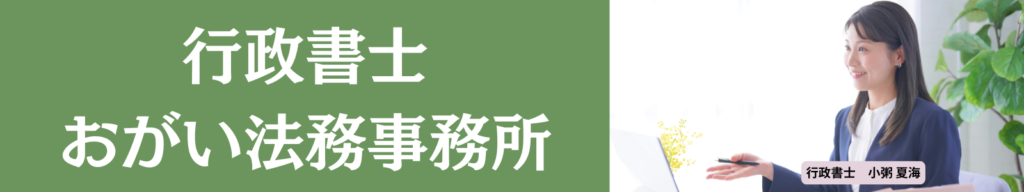
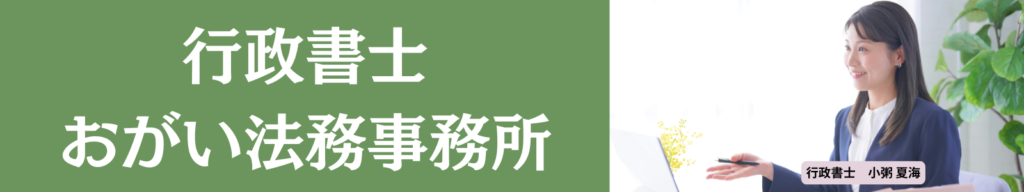
遺留分とは?
例えば・・・
相続手続きの際、遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されますが、「誰か1人に全財産を相続させる」といった内容が書かれていたら、他の家族が困ってしまいます。
このような内容の遺言書があった場合でも、遺族が一定の財産を相続する権利が法律で決められています。最低限の生活を保障され、不公平な遺産分割を防ぐ仕組みとなっています。
遺留分を請求できる人の範囲と割合
遺留分を請求できる人
- 配偶者
- 子や孫などの直系卑属
- 親や祖父母などの直系尊属
遺留分を請求できる割合
相続人の構成によって変わります。法定相続人については以下の記事で詳しく説明しています。
| 相続人 | 遺留分の割合 |
|---|---|
| 配偶者 | 法定相続分の半分 |
| 子供 | 法定相続分の半分 |
| ご両親 | 法定相続分の1/3※ |
| 兄弟姉妹 | なし |
※直系尊属である親や祖父母は、第一順位の相続人である子がいない場合に限り相続人となります。遺留分の請求権に関しても、子がいない場合に限って認められることになります。
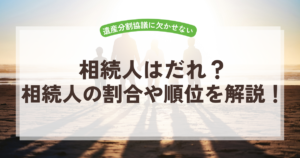
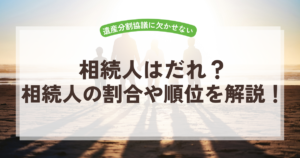
“民法1042条”
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
遺産に不動産がある場合は要注意


不動産の価値は、相続が開始された時点での市場価値に基づいて算定され、相続財産の総額に大きな影響を与えるため、特に注意が必要です。
相続財産の総額は遺留分の金額に大きく影響があるからです。
物件の状態や立地条件によって不動産の価値の評価は変動するため、正確に市場価値を把握することが重要です。
まとめ
本記事では、遺留分の基礎知識から請求できる人の範囲や割合を説明しました。
故人が遺言で遺産の分配を決めてあったとしても、遺留分は侵害されないように法律で守られています。
しかし、遺留分を侵害されたからといって、相続人は必ず遺留分の請求をしなければならない、というものではありません。遺産分割に伴う複雑な手続きや相続人間のトラブルを考慮したうえで、遺留分の権利の行使をすることをオススメします。
必要に応じて専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
お気軽にご相談ください
お電話で相談をご希望の方
【受付時間】9:00~18:00(土日祝除く)
メールで相談をご希望の方
【受付時間】24時間※後日連絡いたします
FAXで相談をご希望の方
【受付時間】24時間※後日連絡いたします

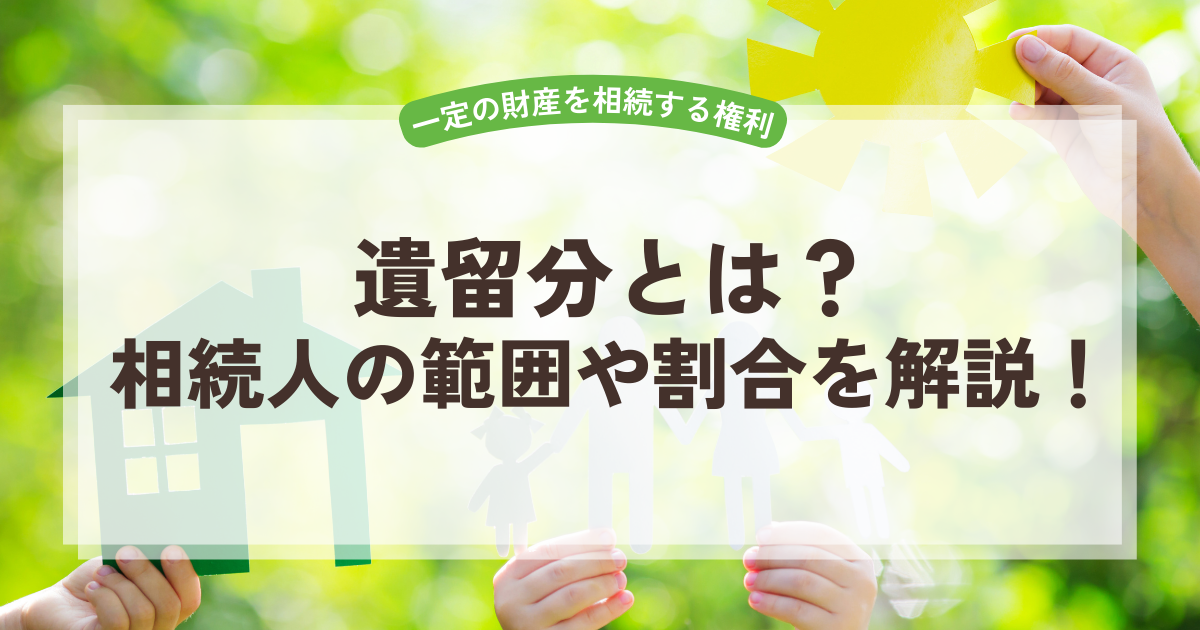
アイキャッチ画像-3-300x158.png)
アイキャッチ画像-300x158.png)