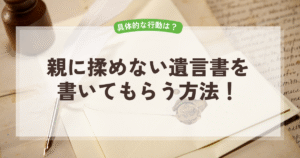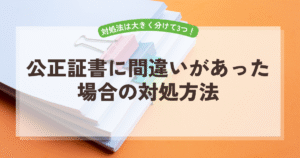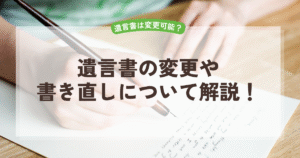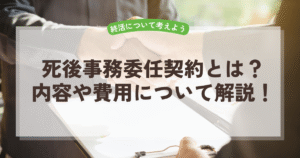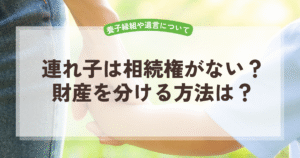静岡県浜松市では、高齢化が進む中で「任意後見契約」いう制度への関心が高まっており、当事務所にも多くのご相談が寄せられています。
認知症などで判断力が低下する前に、自分の意思で将来の支援体制を整えるこの制度は、安心して暮らすための大切な選択肢です。
この記事では、行政書士が制度のしくみと活用事例をわかりやすくご紹介します。
任意後見契約とは?|自分の意思で将来を守る制度
任意後見契約とは、将来、認知症などで判断力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見受任者)を自分で選んでおく制度です。元気なうちに「誰に」「どんな支援をしてほしいか」を自分で決めておけるため、老後の安心につながります。判断力が十分でなくなったときには、任意後見受任者が正式な「任意後見人」として、ご本人の生活や手続きを支える役割を担います。
法定後見制度と異なり、任意後見契約は本人の意思で始めることができるのが特徴です。
契約は公正証書で作成し、実際に支援が必要になった段階で家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約が効力を持ちます。
任意後見契約のしくみ|契約から支援開始までの流れ
まずは、将来支援をお願いしたい人を決めます。家族や親しい知人、または専門職(行政書士など)から、信頼できる方を選びましょう。「自分のことをよく理解してくれている」「誠実に対応してくれる」など、安心して任せられる人が望ましいです。
支援をお願いする人が決まったら、行政書士などの専門家と一緒に契約内容を整理し、公証人と連携して「公正証書」を作成します。この契約では、「どんな支援をしてほしいか」「どこまで任せるか」などを具体的に決めておきます。
契約を結んだだけでは、すぐに支援が始まるわけではありません。ご本人の判断力が低下したとき、家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見監督人が選ばれた時点で契約が正式に発効します。
契約が発効すると、任意後見人がご本人の生活を支える役割を担います。支援内容は契約で定めた範囲に限られ、たとえば、預貯金や不動産などの財産管理や介護サービスの契約や役所への手続き代行等があります。
活用事例|こんな方に選ばれています
一人暮らしの88歳女性Aさんの事例
Aさんは浜松市にお住まいの88歳の女性。お子さんはおらず、遠方に住む息子さんが唯一のご親族です。これからの暮らしをどう守っていけばいいのかと、不安があり、将来への備えを真剣に考えるようになったようです。
特に心配されていたのは、判断力が低下したときの生活や財産管理、そしてご自身が亡くなった後の葬儀や供養のこと。遠方に住む息子さんにすべてを任せるのは申し訳ないというお気持ちもあり、「今のうちにできることをしておきたい」とご相談にいらっしゃいました。
そこで、Aさんの想いに寄り添いながら、以下のような制度設計をご提案しました。
任意後見契約
当事務所と、財産管理や福祉サービスの契約などを委任する内容で契約を結びました。判断力が低下したときには、家庭裁判所の手続きを経て、正式に支援が始まる仕組みです。
死後事務委任契約
当事務所と、葬儀、納骨、家財整理、各種解約手続きなどを委任する契約を結びました。Aさんは「自分の死後もきちんと整理されると思うと安心」と話され、預託金をご準備されました。
公正証書遺言
財産の分配について遺言書を作成し、遺言書の付言事項にAさんの想いを込めて作成しました。
このように、Aさんは「今の不安」「将来の支援」「死後の手続き」までを一つひとつ丁寧に整え、総合的な安心のしくみを築かれました。
高齢夫婦Bさん夫妻の事例
Bさんご夫妻は、静岡県内にお住まいの子供のいないご夫婦です。お互いが元気なうちは特に困ることはありませんが、「もしどちらかが先に判断力を失ったら」「二人とも支援が必要になったら」と、将来への備えに不安を感じておられました。夫婦で支え合えるしくみと、必要なときに外部の専門家に頼れる体制を整えることになりました。
相互任意後見契約
まず、Bさんご夫妻はそれぞれが互いを第一任意後見人に指定し、万が一どちらかが先に判断力を失った場合でも、もう一方が支援できるようにしました。さらに、当事務所(行政書士)を予備的(第二)任意後見人として指定し、家族では対応が難しい法的手続きや財産管理も安心して任せられるような仕組みづくりをしました。
よくある質問
- 認知症になったらすぐに契約が発効するの?
-
いいえ、すぐには発効しません。
任意後見契約は、契約を結んだだけでは効力を持ちません。ご本人の判断力が低下したときに、家庭裁判所へ「任意後見監督人の選任申立て」を行い、監督人が選ばれた時点で契約が正式に発効します。この仕組みによって、支援が必要なタイミングを見極めながら、適切な人が支援を開始できるようになっています。 - 任意後見人が勝手に財産を使うことは?
-
不正利用を防ぐ仕組みが整っています。
任意後見契約が発効すると、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。この監督人は、任意後見人の活動を定期的にチェックし、報告書を受け取るなどして不正がないかを見守ります。また、契約時に「支援の範囲」や「使える財産の種類」などを明確に定めておくことで、後見人が勝手に判断する余地を減らすことができます。 - 契約後に内容を変更できる?
-
判断力があるうちは、変更や解除が可能です。
任意後見契約は、契約者本人の意思で結ぶものです。そのため、判断力がしっかりしている間であれば、契約内容の見直しや後見人の変更、契約の解除も可能です。ただし、契約書は公正証書で作成されているため、変更や解除には再度公証人との手続きが必要になります。行政書士が間に入ることで、スムーズに進めることができます。 - 費用はどれくらいかかる?
-
内容によって異なりますが、主な費用は以下の通りです。
公正証書作成費用(公証人手数料+印紙代など)約20,000〜50,000円程度、行政書士報酬(契約書作成・手続き支援)約50,000〜100,000円程度(事務所による)任意後見監督人報酬(発効後、家庭裁判所が定める)月額10,000〜30,000円程度(内容による)こちらの金額はあくまで目安です。実際の費用は契約内容や地域、支援の範囲によって異なります。
行政書士に相談するメリット|安心の準備をサポート
任意後見契約は法的な制度であるため、専門的な知識と丁寧な支援が欠かせません。行政書士に相談することで、制度のしくみをわかりやすく説明してもらえるだけでなく、公正証書の作成やご家族との調整も、安心して進めることができます。
特に、一部の行政書士が所属する「公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター」では、任意後見契約をはじめとする成年後見制度の普及と支援に取り組んでおり、専門職としての倫理と実務経験を活かしたサポートが受けられます。
ご本人の不安に寄り添いながら、「今の安心」「将来の備え」「死後の手続き」までを一つひとつ丁寧に整えることで、安心して老後を迎える準備ができます。
まとめ
「まだ元気だから」「家族に迷惑をかけたくないから」と思う方こそ、今のうちに準備しておくことで、安心して日々を過ごすことができます。
当事務所では、浜松市を中心に、地域に根ざした支援を行っています。制度のしくみをやさしくご説明しながら、ご本人の想いやご家族の状況に合わせて、無理のないかたちで制度設計をお手伝いします。
「制度のことがよくわからない」「何から始めればいいか不安」という方も、どうぞご安心ください。
まずはお話をうかがうところから、一緒に考えていきましょう。
お気軽にご相談ください
お電話で相談をご希望の方
【受付時間】9:00~18:00(土日祝除く)
メールで相談をご希望の方
【受付時間】24時間※後日連絡いたします
FAXで相談をご希望の方
【受付時間】24時間※後日連絡いたします

アイキャッチ画像-5.png)
アイキャッチ画像-4-300x158.png)
アイキャッチ画像-2-300x158.png)