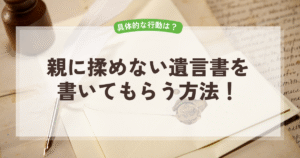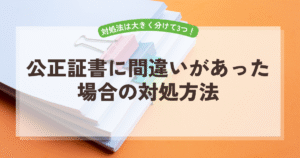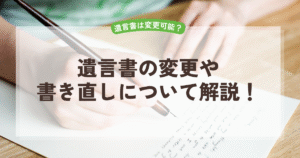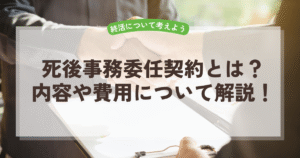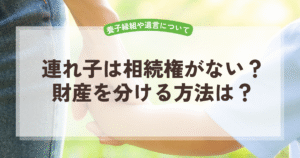「もしもの時」に備えて、今できることは何でしょうか。
相続や認知症など、将来への不安は誰にでもあるものです。でも、「何から始めればいいのかわからない」「専門家に相談するのは少しハードルが高い」と感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、行政書士が生前にやっておくべき5つの対策をわかりやすく解説します。
財産の棚卸と整理
「自分の財産って、どれくらいあるんだろう?」そう思ったことはありませんか?
財産の棚卸とは、今ある資産や負債を一度整理して、全体像を把握することです。これは、遺言書や家族信託、後見契約などを考えるうえで、最初にやっておきたい大切なステップです。
なぜ棚卸が必要なのか
- 財産の全体像がわかる
-
預貯金、不動産、保険、有価証券、負債などを一覧にすることで、「何をどう分けるか」「誰に託すか」が明確になります。
- 相続人への負担を減らせる
-
亡くなった後に家族が通帳や契約書を探し回る必要がなくなり、手続きがスムーズになります。
- トラブルの予防につながる
-
「知らなかった財産があった」「誰が管理していたのか分からない」といった誤解を防げます。
棚卸のポイント
| 項目 | チェック内容の例 |
|---|---|
| 預貯金 | 銀行名、支店名、口座番号、残高 |
| 不動産 | 所在地、登記内容、評価額、利用状況 |
| 保険 | 保険会社、契約内容、受取人 |
| 有価証券 | 株式・投資信託の銘柄、証券会社 |
| 負債 | 借入先、残債、返済条件 |
| その他 | 貴金属、骨董品、デジタル資産など |
遺言書の作成
遺言書は、亡くなった後に「自分の意思」を法的に残す唯一の手段です。作成しておくことで、以下のようなメリットがあります。
なぜ遺言書が必要なのか
- 相続トラブルの予防
-
兄弟間での不動産の分配、事業承継の明確化などをしておくことで、相続人同士の争いを防ぎ、円満な相続をすることはできます。
- 意思の尊重と安心感
-
「誰に何を残したいか」「どのように分けたいか」を明確にすることで、家族も故人の思いを尊重しやすくなります。
- 法定相続では対応できないケースに対応
-
内縁の配偶者、事実婚、特定の子どもへの配慮など、法定相続ではカバーできない事情にも対応しています。
- 遺産分割協議の負担軽減
-
遺言があることで、相続人が話し合う必要がなくなり、手続きがスムーズになります。
遺言書の種類
遺言書には主に3つの種類があり、それぞれに特徴があります。
以下の記事でも詳しく解説しておりますので参考にしてみてください。
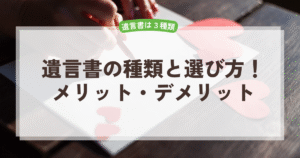
遺言書の選び方
認知症などのリスクがある方、財産が多い方、相続人が複数いる方におすすめです。
令和2年から始まった「自筆証書遺言保管制度」を使えば、紛失や改ざんのリスクを減らせます。
事業承継、障がいのある子への配慮、相続人以外への遺贈などは、法的な設計が重要です。
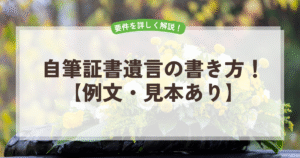
行政書士ができるサポート
遺言書は「書けば終わり」ではなく、法的な有効性と実現可能性が重要です。
- 1.文案作成・内容の整理
-
遺言書の作成にあたっては、まずご本人の意思を丁寧にヒアリングすることから始まります。
どのような思いで財産を分けたいのか、誰に何を託したいのか、その背景にある感情や価値観も含めて、じっくりと伺います。
そのうえで、法的に有効な文案を作成し、安心して残せる形に整えていきます。
財産の種類や相続人との関係性を踏まえた分配案をご提案しながら、感謝の言葉や家族へのメッセージなど、感情面にも配慮した表現を工夫することで、形式だけでなく「心が伝わる遺言書」を目指します。
- 2.証人の手配(公正証書遺言の場合)
-
公正証書遺言を作成する際には、証人の立ち会いが必要です。
信頼できる証人の確保や、当日の立ち会い調整もお任せください。ご本人のご負担を減らすため、公証役場との事前打ち合わせも代行可能です。
- 3.保管方法のアドバイス
-
遺言書は作成後の保管も重要です。
自筆証書遺言の場合には、法務局への保管申請をサポートし、紛失や改ざんのリスクを減らします。
公正証書遺言の場合は、公証役場で原本が保管される仕組みをご説明し、控えの管理方法についてもアドバイスいたします。
任意後見契約の締結
認知症などのリスクに備える
人生の後半に向けて、判断能力の低下に備えることは、安心して暮らすための大切な準備です。
任意後見契約は、ご本人が元気なうちに「将来、判断力が衰えたときに支援してほしい人」を決めておく制度です。
認知症や病気などで意思表示が難しくなった場合でも、あらかじめ選んだ後見人が、財産管理や生活支援などを法的に行えるようになります。
契約の流れとポイント
ご本人が信頼できる人(家族、知人、専門職など)を後見人候補として選びます。継続的な支援が可能か、生活圏が近いか、本人との関係性なども考慮して選定しましょう。
財産管理、生活支援、医療手続き、行政対応など、将来、後見人がどのような支援を行うかを具体的に決めます。
ご本人の希望や生活状況に合わせて、支援範囲を明確にしましょう。
必要に応じて、行政書士が文案作成をサポートします。
公証役場にて「任意後見契約公正証書」を作成します。ご本人と後見人候補が同席し、契約内容を確認・署名します。
契約締結後は、まだ効力は発生しません。
ご本人が元気なうちは、契約は「待機状態」となります。契約書は安全な場所に保管し、家族にも内容を共有しておくと安心です。
ご本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所に申し立てを行います。
裁判所が「任意後見監督人」を選任することで、契約が発効します。ここから後見人による支援が正式に始まります。
行政書士の役割
行政書士は、任意後見契約の準備段階から契約締結まで、幅広くサポートします。
まず、ご本人の希望や生活状況を丁寧にヒアリングし、契約内容の整理と文案作成を行います。
契約書には法的な要件が求められるため、専門的な視点から漏れのない構成を整えます。
また、後見人候補の選定に関する相談も可能です。ご家族以外の第三者を希望される場合や、複数候補がいる場合など、それぞれのメリット・注意点を踏まえてアドバイスいたします。公証役場との事前打ち合わせや、必要書類の準備、当日の同行などもご希望に応じて対応いたします。
任意後見契約は、ご本人の「これからの暮らし方」を守るための大切な制度です。行政書士として、安心して契約を結べるよう、制度の説明から実務まで丁寧に寄り添います。
家族信託の活用
「認知症になったら財産管理はどうなるの?」「子どもに任せたいけれど、贈与はまだ早い…」そんな声が増えています。家族信託は、従来の制度では対応しきれなかった「柔軟な財産管理」を可能にする新しい仕組みです。
家族信託とは?
家族信託とは、ご自身の財産を信頼できる家族(受託者)に託し、決められた目的に沿って管理・運用してもらう制度です。
財産の所有権は受託者に移りますが、使い道や受益はご本人が受け続けます。認知症などで判断力が低下しても、あらかじめ決めたルールに従って財産管理が継続されます。
家族信託のメリット
- 認知症になっても、財産をスムーズに管理できる
-
もし判断力が落ちても、信頼できる家族が代わりに管理できるようになります。銀行口座や不動産の手続きも止まらず、安心です。
- 不動産や事業の引き継ぎがしやすくなる
-
「この土地は長男に」「事業は娘に」など、将来の分け方を柔軟に決めておけます。遺言では難しい「段階的な引き継ぎ」も可能です。
- 家族の気持ちがすれ違わないようにできる
-
あらかじめルールを決めておくことで、「誰が何をするのか」が明確になり、家族間の誤解や争いを防げます。
- 相続や後見制度ではできないことにも対応できる
-
「障がいのある子の生活を長く支えたい」「配偶者に生活費を渡しながら、最終的には子に財産を渡したい」など、細かな希望にも対応できます。
エンディングノートの記入
エンディングノートは、法的な効力こそありませんが、「自分の人生をどう締めくくりたいか」「大切な人に何を伝えたいか」を整理するための、心の記録帳です。
- 医療・介護の希望(延命治療の有無、入院・施設の希望など)
- 葬儀やお墓の希望(宗教、形式、埋葬方法、墓地の場所など)
- 大切な人へのメッセージ(感謝の言葉、伝えたい想い、思い出など)
- SNSの扱いなど(SNSの削除・継承方法)
書き始めるタイミングは「思い立った今」
「まだ元気だから」「書くほどのことはないかも」と思っている方こそ、今が始めどきです。
体調や環境が変わる前に、自分の考えを落ち着いて整理できる時間を持つことが、何よりの備えになります。
また、エンディングノートを書くことで、自分自身の価値観や人生観が見えてくることもあります。ご家族にとっても、「こんなふうに考えていたんだ」と、故人の思いを受け取る大切な手がかりになります。
すべてを一度に書く必要はありません。思いついたことから、少しずつ書き足していくスタイルで大丈夫です。
まとめ
相続や認知症など、将来への不安は誰にでもあるものです。でも、少しずつ準備を始めることで、「もしもの時」に慌てず、安心して迎えることができます。
- 財産の棚卸で、今あるものを見える化
- 遺言書で、自分の意思をしっかり残す
- 任意後見契約で、判断力の低下に備える
- 家族信託で、柔軟な財産管理を実現
- エンディングノートで、想いを言葉にして伝える
まずは一歩。ご自身やご家族の未来のために、できることから始めてみませんか?
当事務所では、制度の説明だけでなく、気持ちに寄り添ったサポートを大切にしています。
浜松市を中心に、静岡県西部エリアでの出張相談も柔軟に対応しております。お気軽にご相談ください。
お気軽にご相談ください
お電話で相談をご希望の方
【受付時間】9:00~18:00(土日祝除く)
メールで相談をご希望の方
【受付時間】24時間※後日連絡いたします
FAXで相談をご希望の方
【受付時間】24時間※後日連絡いたします

アイキャッチ画像-2.png)
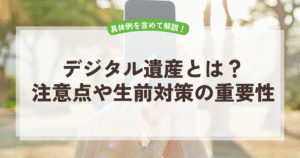
アイキャッチ画像-5-300x158.png)
アイキャッチ画像-4-300x158.png)