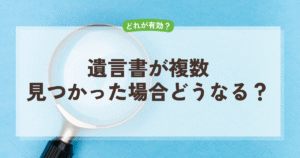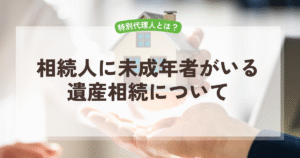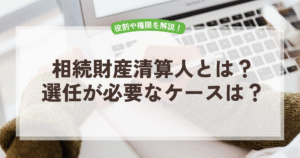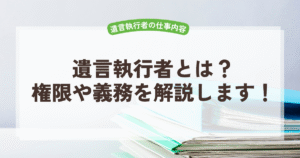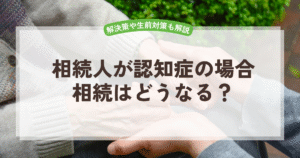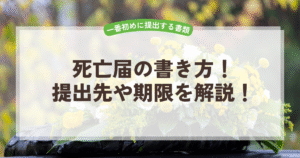相続手続きにおいて「遺言書」と「遺産分割協議書」の役割は重要です。
しかし、遺言書が存在する場合でも遺産分割協議書を作成できるか疑問に思う方も少なくありません。
本記事では、専門的な視点からその条件や注意点を解説します。
遺言書があるとどうなるのか?
亡くなった人が有効な遺言書を作成していれば、遺産分割協議は不要になり、遺言書の内容に基づいて進めるのが原則です。
遺言書があっても遺産分割協議ができるか?
被相続人の意思を尊重して、その内容どおりに相続手続きを進めるのが原則ですが、遺言書が遺されていたからといって、必ずしもその内容に従わなければならないわけではありません。
次の条件を満たしている場合については、遺言書があったとしても遺産分割協議により、遺言と異なる遺産分割を行うことが可能です。
遺言書があっても遺産分割協議ができる条件
相続人全員の合意があること
相続人全員が遺言書の内容を十分理解した上で合意すれば、遺言内容と異なる遺産分割協議書を作成することができます。
相続人の一部に遺言書の内容を隠して遺産分割協議をしても、相続人全員の同意を得たことにはなりません。たとえ遺言書の内容に関わらない相続人であっても、遺産分割協議をするなら遺言書の内容を確認してもらいましょう。
受遺者と遺言執行者の同意が得られること
遺言書で相続人以外の第三者に財産を遺贈することが書かれている場合は、その受遺者が遺産分割協議による相続に合意する必要があります。
また、遺言書で相続人以外の人を遺言執行者に指定している場合は、遺言執行者の同意が必要になります。
遺言書が遺産分割を禁止していないこと
遺言書に「遺産分割の禁止」が記載されていないことが一つの条件となります。
民法907条(遺産の分割の協議又は審判)
共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
まとめ
遺言書があっても、相続人全員が合意すれば遺産分割協議書を作成することは可能です。ただし、受遺者や遺言執行者が関与している場合や、遺言書に特定の条件が記載されている場合には専門家のサポートを受けながら、慎重に手続きを進めましょう。
当事務所では、静岡県西部を中心に相続手続きをサポートしております。
お気軽にご相談ください
お電話で相談をご希望の方
【受付時間】9:00~18:00(土日祝除く)
メールで相談をご希望の方
【受付時間】24時間※後日連絡いたします
FAXで相談をご希望の方
【受付時間】24時間※後日連絡いたします

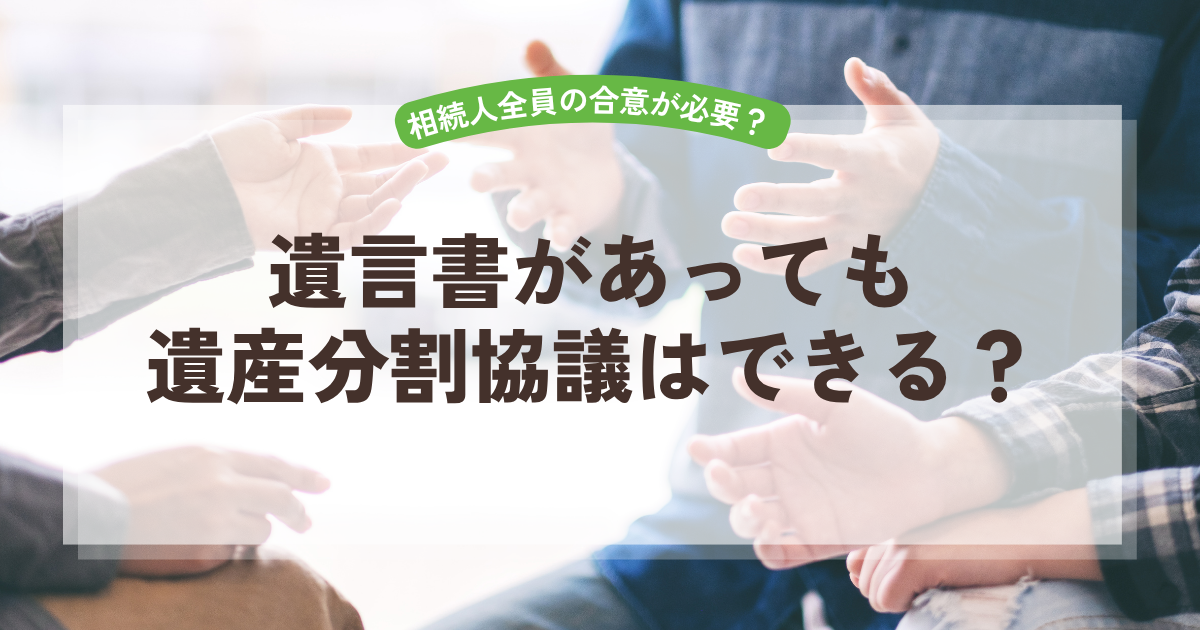
アイキャッチ画像-3-300x158.png)
アイキャッチ画像-300x158.png)